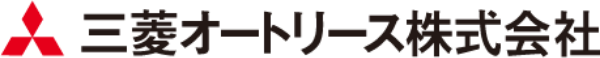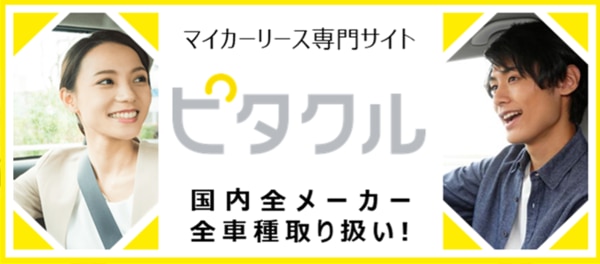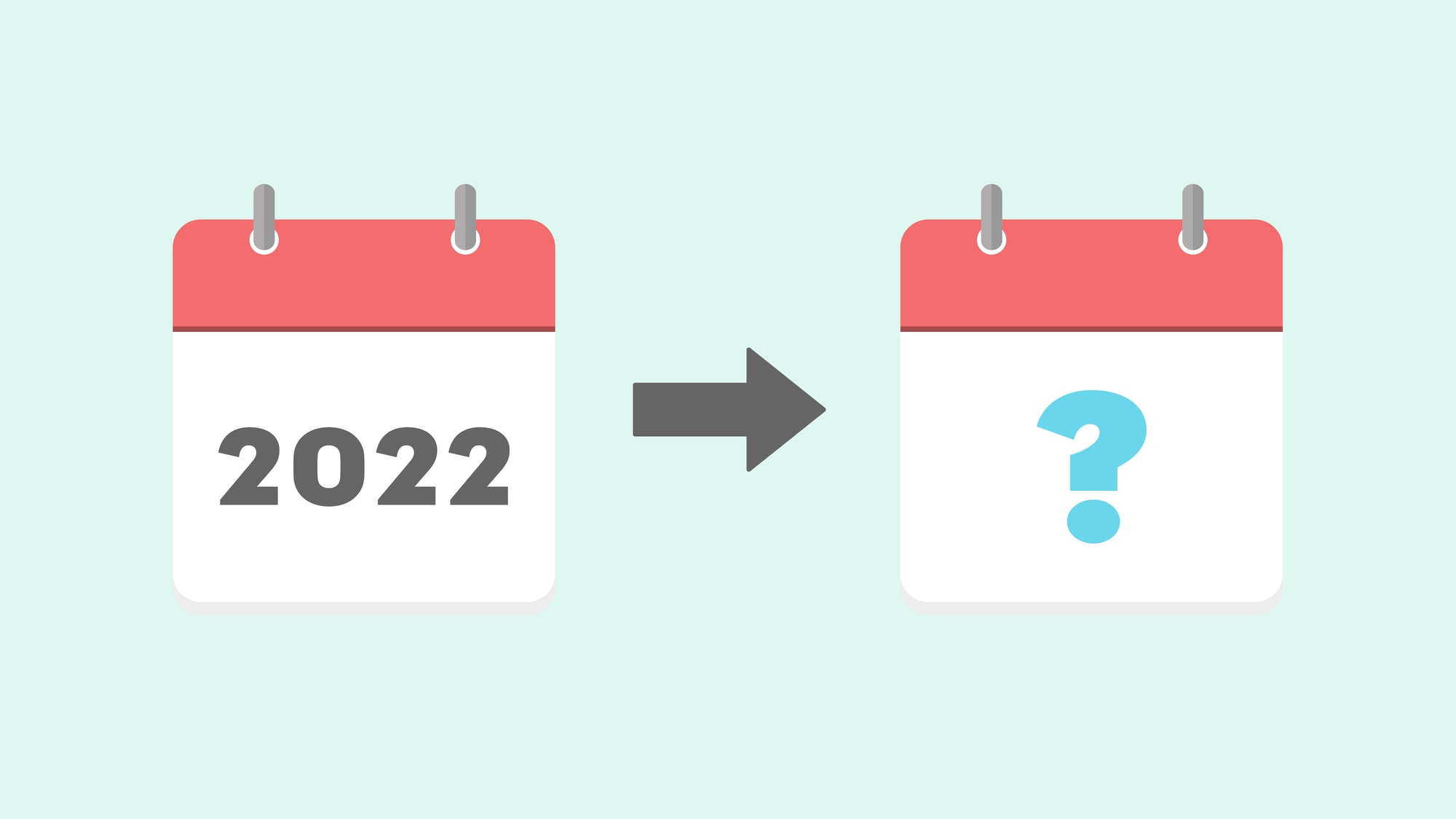
アルコールチェッカー使用の義務化が延期となりました。― まだ間に合う対策とは?
2022年4月より改正道路交通法施行規則の施行により、「白ナンバー」事業者にもアルコール
チェックが義務化されました。
当初は、2022年10月からアルコールチェッカ―(検知器)を使ったアルコールチェックの義務化
が開始される予定でしたが、9月14日に警察庁から、アルコール検知器の供給状況等を踏まえ、
『当分の間、適用しない』との発表がされました。
義務化の具体的な時期は示されませんでしたが、アルコール検知器が市場に十分に流通する見通
しが立った時点で、早期に適用される見込みのようです。義務化適用が延期になっている今のうち
に、アルコール検知器を使った確認と結果の記録・保存を徹底するための「社内の対策」について
ご案内いたします。
目次[非表示]
義務化・延期になった内容
運転前後の運転手に対し、アルコール検知器を使用して、酒気帯びの有無を確認すること
(道路交通法施行規則 第6号)
アルコール検知器を常時有効に保持すること
(道路交通法施行規則 第7号)
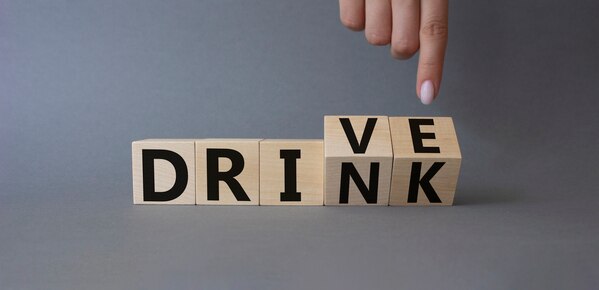
対策①:アルコール検知器でいつでも確認できる体制つくり
対象企業の安全運転管理者は、従業員が業務で社用車を運転を開始または運転後に、アルコール検
知器を使用して、酒気帯び有無の確認ができる体制を整えておく必要があります。
安全運転管理者が外出等の不在の場合に備えて、対応できるように代行できる担当者を選定して
おきましょう。
■アルコール検知器による確認実施ができる人
安全運転管理者、副安全運転管理者、安全運転管理者の業務を補助する者
対策②:勤務実態に合わせた検知器の導入
事業所から社用車の運転を開始する職種もあれば、出張や自宅からの直行直帰で運転を開始する職
種の従業員がいらっしゃる企業様も少なくないかと思いますが、このようなケースであってもアル
コール検知器による確認が必要となります。出張や直行直帰が多い職場の場合は、対面での確認が
難しくなるので、対象者用に携帯タイプのアルコール検知器を準備しましょう。カメラやモニター
を併用することでチェックが完了したとみなされるためです。
対策③:アルコール検知器の定期点検
今回の改正では、アルコール検知器による確認の他、「常時有効に保持する」と定められていま
す。いつでも正常にアルコールを検知できる状態を保持する必要があるので、日常点検と定期メン
テナンスが必要不可欠となります。取り扱い説明書を確認の上、定期点検をかかさないように点検
方法を確認しておきましょう。
毎日点検 |
本体に損傷や異常はありませんか? |
正常に電源が入りますか? | |
画面に確認値が表示されますか? | |
マウスピースや息を吹きかける箇所は汚れていませんか? | |
週に1度点検 |
酒気帯びしていない状態で安全運転管理者が使用した場合に、アルコールを誤検知しませんか? |
|
アルコールを含む液体※を吹きかけた場合に、アルコールを検知できますか?
(アルコール成分を含むうがい薬等を使ったテストがおススメです)
|
※その他、正常作動の確認方法および操作方法詳細は検知器の取扱説明書を確認してください。
※故障や異常がある場合は、速やかにメーカー指定のサービスセンター等に確認しましょう。
※検知器には、有効期限や使用回数の上限が設定されているタイプが多いようです。
有効期限や残りの使用回数をこまめに確認し、交換時期の目安を把握しておきましょう。
※故障に備えて、予備機を準備しておいた方が安心です。
対策④:確認結果の記録・保存
アルコール検知器での確認結果は、記録し、一年間保存する必要があります。
指定された書式はありませんが、以下の内容を記録しましょう。
■記録内容
1 |
確認者名 |
2 |
運転者名 |
3 |
業務で使用する自動車の登録番号(識別番号) |
4 |
確認日時 |
5 |
確認方法 ・アルコール検知器の使用の有無<延期> ・対面でない場合はカメラ・モニター、またはスマートフォンや携帯電話などを使用 |
6 |
酒気帯びの有無 |
7 |
指示事項 |
8 |
その他必要な事項 |
記録方法は書面、電子データ等の指定はありませんが、従業員の人数や事業所の数が多い場合には
紛失防止や記録内容をすぐに確認できる点で、システムの活用はとても有効です。
三菱オートリースでは、「アルコールチェック」機能を追加した「テレマティクスサービス」を
展開しております。従業員の方が、スマートフォンを使ってアルコールチェックの確認結果を記録
できる機能もございますので、ご興味がある方は、ぜひとも下記セミナーにご参加ください。
まとめ
飲酒運転は、従業員の安全を脅かすと共に、企業の存続にも大きく影響を及ぼす可能性のあるも
のです。飲酒運転撲滅のためには、企業全体で、アルコールチェック義務化の主旨をしっかりと理
解した上で、アルコールチェックを徹底し継続していくことが必要です。
また、運転手の運転前後の目視による確認とアルコール検知器による測定を実施することで、
運転手の体調や疲労の状況も把握できますので、飲酒運転だけではなく、重大事故を回避する防止
策となりえます。
今一度、アルコール検知器の取り扱い方法や点検方法を確認すると共に、4月から義務化された
酒気帯びの確認や結果の記録・保存が正しく実施できているかについても見直しをしておくと安心
です。
※当ページでは、2022年9月の警察庁の発表をもとに作成しております。最新情報及び、改正内容
詳細は、警察庁サイトや各都道府県警察サイトのご案内をご確認ください。